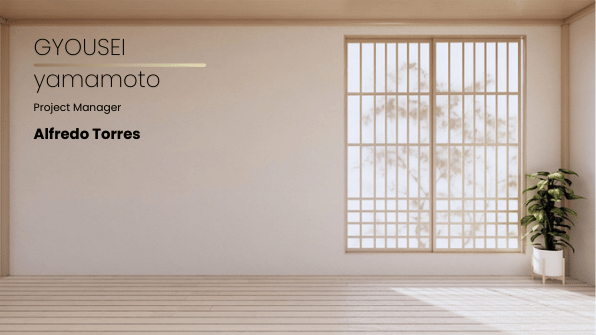目次
✅ 行政書士による相続人捜索の基本的なアプローチと段取り
① 受任・事情聴取(ヒアリング)
- 依頼人(通常は遺言執行者、相続人、関係者など)から事情を聴取。
- 被相続人の氏名、生年月日、本籍地、最終住所、死亡日時などを確認。
- 既知の相続人がいれば、その情報も収集。
② 被相続人の戸籍調査
戸籍謄本の収集が相続人調査の核心です。
ステップ:
- 死亡時の戸籍(除籍・改製原戸籍)を取得
→ 本籍地の市区町村役場から取り寄せ。 - 出生まで遡って戸籍をたどる
→ 転籍がある場合は、その都度本籍地の役所に戸籍を請求。
→ 明治・大正・昭和初期まで遡ることもあります。 - 結婚・離婚・養子縁組などの履歴もチェック
→ 誰が法定相続人に該当するか確認するため。
📌 目的:被相続人の子、配偶者、親、兄弟姉妹など、相続権のある者を網羅的に特定する。
③ 相続関係説明図の作成
戸籍から得た情報を基に、家系図のように相続関係を図式化。
- 誰が法定相続人であるか、順位と人数を明確にする。
- 複雑な家系(再婚、認知、養子縁組など)の整理に重要。
④ 相続人の現在の所在調査
戸籍で相続人が判明しても、住所が不明な場合には以下の方法で調査します。
主な方法:
- 住民票の取得(行政書士が職務上請求可能)
- ただし、正当な職務目的があることが必要(例:相続手続に必要なため)。
- 戸籍の附票の取得
- 本籍地から移動した住所履歴が分かる。
- 登記簿、電話帳、SNSなどの調査(民間調査手段)
📌 注意: 行政書士は探偵業務や違法な個人情報収集は行えません。正当な公的資料で調査を行います。
⑤ 相続人への連絡・通知
- 書面や電話などで相続人に連絡。
- 遺産分割協議への参加要請。
- 必要に応じて、遺産内容や法的説明を行う。
⑥ 相続人が判明しない・行方不明な場合
- 不在者財産管理人の選任(家庭裁判所に申立)
- 失踪宣告の申立
- 特別縁故者への財産分与(相続人がいない場合)
🔍 補足:行政書士の限界と連携
- 行政書士は戸籍や住民票の職務上請求権がありますが、調停や裁判所提出書類の作成には制限があります。
- 弁護士や司法書士と連携する場合もあります(例:法定相続情報一覧図の作成、登記申請など)。
✅ まとめ:行政書士の相続人調査段取り
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 依頼受任・事前ヒアリング |
| 2 | 戸籍の収集と出生までの遡り |
| 3 | 相続関係説明図の作成 |
| 4 | 住民票・戸籍附票等で所在調査 |
| 5 | 相続人への通知・連絡 |
| 6 | 不明・不在の場合の法的対応(家庭裁判所申立など) |